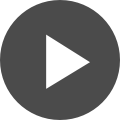ワイヤレス機器およびIoT機器の自動発生EMIの特性評価およびトラブルシューティング - AltiumLive 2022
今日のポータブル機器、モバイル機器、IoT機器では、EMIの原因となる複数のエネルギー源が搭載されていることがかなり一般的になっています。これらのエネルギー源から発生するEMI (自動インタラクティブ配線) は、携帯電話やGPSなどのワイヤレスモジュールの受信性能に影響を与えることがあります。このプレゼンテーションでは、これらのエネルギー源による結合を特定し、特性を明らかにし、低減するための方法について説明します。無償評価版のAltium DesignerでPCBを設計するには、こちらにアクセスしてください:https://www.altium.com/altium-trial-flow
ハイライト:
- 携帯電話やワイヤレス製品で自動発生するEMIの問題点
- 自動発生するEMIのトラブルシューティング3ステップ
- ナローバンドとブロードバンドにおけるEMIの違い
- 適切なスタックアップと分割による最適な基板設計
- 還流伝導電流の経路の重要性
こちらもご覧ください:
トランスクリプト:
ケネス・ワイアット:
こんにちは、コロラド州在住のEMCコンサルタント、ケネス・ワイアットです。今日は、ワイヤレス機器やIoT機器の自動生成するEMIの特性評価とトラブルシューティング方法についてお話しします。AltiumLive 2022 CONNECTに招待してくださったAltiumに感謝します。私の経歴について詳細は資料をご覧ください。簡単に申し上げると、EMCトラブルシューティングやテストについて数冊の書籍を共著している他、EDN誌、Signal Integrity Journal誌、Interference Technology誌に記事を執筆しています。最新の出版物は、Amazonで販売している『EMC Troubleshooting 三部作』です。エミッションに関する第2巻には、無線の自動干渉に関する章がありますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。
ケネス・ワイアット:
では、なぜ自動生成するEMIがワイヤレス機器や携帯電話などで問題になるのでしょうか?プラットフォームや自動干渉は、ワイヤレス機器やIoT機器の製品設計者が今日直面している最大の課題の1つです。例えば、Apple社には、無数にあるワイヤレス機器の受信モジュールへの自動干渉を緩和するために、何十人ものデセンスエンジニアが在籍しています。自動発生するEMIの発生源トップ3は、システムクロック、DC-DCコンバーター、デジタルバスノイズで、その中でもDC-DCコンバーターが圧倒的な発生源です。多くの企業は、自社製品にセルラーLTEを搭載しています。携帯電話会社では、製品をシステムに搭載する前に、全等方感度(TIS)と呼ばれる一定の受信感度を必要としています。自動発生するEMIは、感度の高い受信機と結合し、感度を低下させるため、TISテストに失敗することがあります。TISの最小値は約マイナス99dBmで、これもアンテナ効率に依存します。このテストに関する詳細情報へのリンクをいくつか追加しました。
ケネス・ワイアット:
ワイヤレス機器やIoT機器の結合経路には、ケーブルからの放射、ワイヤやトレースからの伝導、容量性、誘導性の4つの可能性がありますが、これらは通常、寄生結合です。こちらの4つの結合経路を示した図をご覧ください。ほとんどのポータブルワイヤレス機器にはケーブルがないため、最後の3つの電動結合、容量結合、誘導結合は通常、PCB上で起きます。PCBの設計については、さらに詳しくご紹介します。
ケネス・ワイアット:
長い年月をかけて、私は自動発生するEMIのトラブルシューティングに役立つ、3つのシンプルなステップを開発してきました。本来は放射性物質の評価のために開発されたものですが、同じ手法で自動発生するEMIの特性を評価することができます。ステップ1では、近接場プローブを使ってPCB上の高調波エネルギー源を特定し、その放射の特性を記録します。ステップ2では、RF電流プローブを使用して、システムケーブルの電流を測定します。ケーブルは送信アンテナとして機能し、高調波エネルギーを放射することがよく知られています。同じ放射特性を記録します。ステップ3では、近くのアンテナを使って、PCBやケーブルから放射される実際の高調波エネルギーを測定します。私は通常、携帯電話やGPSの帯域で何かを観察する際に、最初は10~1500メガヘルツを見ます。それぞれのステップを簡単に見てみましょう。
ケネス・ワイアット:
ステップ1では、中型のH-Fieldプローブを使って、主要なエネルギー源を特定し、その高調波の特性を理解します。自己干渉の特性を評価するにあたって、まず全体像を把握するために10メガヘルツから1500メガヘルツまでをご紹介します。近接場プローブを使って検査すると、基板上のどのエネルギー源がGPSや携帯電話の無線帯域にEMIを発生させているかがわかります。この例では、ナローバンドのイーサネットのクロック高調波と、DC-DCコンバーターからの広帯域EMIが組み合わされています。
ケネス・ワイアット:
一般的にEMIには、ナローバンドとブロードバンドの2つの形態があります。ナローバンドのEMIは、調和的に関連した一連の狭いスパイクで表され、主にシステムクロックにより発生します。この場合はイーサネットクロックにより発生しました。ブロードバンドのEMIは、全体的なノイズフロアの増加としてよく現れますが、実際には、いくつかの広い共振ピークと混ざり合って見えるような、間隔の狭い一連のスイッチング高調波で構成されています。測定規格で規定されている典型的な120キロヘルツの分解能帯域幅を使用する場合、ブロードバンドのEMIは通常、データバスのアクティビティやDC-DCコンバーターによって発生します。そして、これらは通常、受信機の干渉の主な原因となっています。
ケネス・ワイアット:
次に、特定の携帯電話受信機のダウンリンク帯域に注目します。これは、AT&Tの帯域5、840から860メガヘルツです。黄色のトレースはシステムのノイズフロアで、水色と紫のトレースは2つのDC-DCコンバーターを測定しています。1つのコンバーターは、ノイズフロアから25dB上回っており、経験上、これが携帯電話の受信機と結合された場合、TISの感度テストで不合格になってしまいます。ステップ2では、RF電流プローブを使用して、ケーブルと結合された高周波の高調波電流を測定します。IoT機器にIOケーブルや電源ケーブルがある場合、これらは調和振動場を直接アンテナに放射しやすくなります。こちらは近接場プローブを使った時と同じ、ブロードバンドまたはナローバンドです。
ケネス・ワイアット:
近接場プローブと電流プローブからの潜在的な放射の特性を評価できたら、ステップ3では、調和振動場が放射されているかどうかを確認するために、間隔の近いシンプルなアンテナを使用します。より弱い高調波を観測するためには、アンテナをかなり近づける必要があるかもしれません。その例については、後ほどのケーススタディでご紹介します。Kent Electronics社は、シンプルで低コストのPCBブロードバンド・アンテナのサプライヤーです。リンク先の記事では、アンテナを卓上の三脚に取り付けるためのPVCアダプターの作り方が紹介されています。数多くの無線機器を測定した結果、自然発生するEMIは、主にDC-DCコンバーターに起因することがわかりました。現在のDC-DCコンバーター回路の多くは、比較的大きなブロードバンドEMIを発生させる可能性があります。
ケネス・ワイアット:
では、なぜDC-DCコンバーターはノイズが多いのでしょうか?これらコンバーターのスイッチング周波数は1〜3メガヘルツとかなり低いのですが、立ち上がり時間はナノ秒単位で、1.5ギガヘルツをはるかに超えるEMIを発生させる可能性があります。これらの回路がRFモジュールやアンテナに近接していたり、結合していたりすると、受信性能に影響を与える可能性があります。この例は、典型的な降圧コンバーターです。S1が閉じ、S2が開くと、赤いループに交流電流が流れます。S1が開き、S2が閉じると、青いループに交流電流が流れます。入力コンデンサーと2つのスイッチで構成される緑のループには、サイクルごとに交流電流が流れていることにご注目ください。そのため、EMIを抑えるためには、このループの面積を最小限にしないと、このループがアンテナのように放射されてしまいます。
ケネス・ワイアット:
右のレイアウト例では、緑で示した「ホット」ループがサイズと面積を縮小しています。これは良いレイアウトです。私がDC-DCコンバーターのEMI特性を評価する際に使用している手法の1つに、中型のH-Fieldプローブを用いて各スイッチドコイルを測定するというものがあります。これには、オシロスコープのプローブで回路を短絡させることなく測定できるというメリットがあります。私は、これを「非侵襲的プロービング」と呼んでいます。最良の結合を実現するプローブを適切な向きで、各スイッチングコイルの上に平らに置くことで、最も多くのフラックスラインと結合させることができます。
ケネス・ワイアット:
回路図を見て、コイルLにかかる電圧波形VLを測定しようと考えたとします。スイッチドコイルとH-Fieldプローブの間には、未知の結合相互インダクタンスMが存在します。コイルに流れる電流ILは、上の式、「1/L ∫ VL dt」で示されることがわかっています。プローブポートの出力電圧は、ILの導関数のM倍、またはMをLで割った値のVL倍になります。つまり、出力電圧はコイル電圧VLに比例します。この事実を利用して、次のスライドで見るように、スイッチド波形のすべての重要なEMI特性を記録することができます。プローブの帯域幅は、測定値に影響を与えない程度のものです。
ケネス・ワイアット:
ここでは、上のトレースでH-fieldプローブを使ってプロービングした場合と、下のトレースで高周波アクティブオシロスコーププローブを使い、スイッチノードに直接接続してプロービングした場合を比較しています。パルスの振幅以外のEMI関連のその他の特性、つまり、立ち上がり時間、パルス幅、周期、そしてリング周波数はすべて同じです。EMI測定で最も重要なのは、立ち上がり時間と立ち下がり時間、そしてリング周波数の2つです。この非侵襲的な技術を使うことで、オシロスコープのプローブを使った場合のミスを防ぎ、コンバーターの解析と特性評価を大幅にスピードアップすることができます。
ケネス・ワイアット:
リンギングが放出スペクトルにかなりの影響を与えていることがわかりました。これは、スイッチモード電源でよく起こる現象です。次の2枚のスライドでご説明します。リング周波数は、製品の放出スペクトルに一致する共振ピークを発生させます。リンギングの原因は、スイッチドモード電源の回路に寄生するインダクタンスとキャパシタンスです。この常駐するピークは、さまざまなワイヤレス帯域や携帯電話が使用するLTE帯域の結合EMIを悪化させることがあります。ここでは、窒化ガリウム系のスイッチ素子を用いた1メガヘルツのDC-DC降圧コンバーターのスイッチド波形を測定しています。測定には、ローデ・シュワルツRTE 1104オシロスコープとRT-ZS10 1.5ギガヘルツのアクティブプローブを使用しています。
ケネス・ワイアット:
周波数が約217メガヘルツの非常に大きなリング波が見えます。そのリングの周波数にクローズアップし、放出スペクトルも表示してみました。電源の入力電流を電流プローブで測定すると、水色のトレースにリング周波数217メガヘルツのピークが確認できました。電源の出力電流を測定すると、217メガヘルツの基本波と434メガヘルツの2次高調波の両方にピークがあり、さらに高調波は携帯電話が使用するLTE帯域にまで及んでいます。1メガヘルツのスイッチング電源による非常に広いブロードバンドの放出スペクトルに注目してください。これは、現在のオンボード・スイッチング・コンバーターに比べて非常に特徴的です。
ケネス・ワイアット:
最近、Y.T.C. Technologies社のEMSスキャナーシステムを購入しました。このスキャナーでは、センサーボード内に小さなH-Fieldループが配列されています。アレイ上にPCBを置くと、電磁界のヒートマップが表示されます。これを使って、基板や付属ケーブル周辺のフィールドを評価するようになりました。今のところ結果は良好で、ワイヤレスボードのホットスポットをマッピングできる、トラブルシューティングツールの1つとなっています。そこで、今日の組み込みプロセッサーに使用されているDC-DCコンバーターが、高感度のオンボード受信機への干渉の主な原因であることを知った上で、DC-DCコンバーターのEMIを低減するためのトップ10の方法を見てみましょう。
ケネス・ワイアット:
アドバイス1:PCBのスタックアップを正しく行うこと。良いPCBの設計には2つの非常に重要なルールがあり、数十年前の一般的な設計はこのルールに従っていませんでした。100キロヘルツ以上では、すべての信号と電力の過渡現象は、トレースとリターンプレーンの間の誘電体空間内での電磁波として伝搬します。ルール1は、電磁波を束ねるために、すべての信号トレースと電源プレーンまたはトレースは、隣接するソリッドリターンプレーンを持たなければならないということです。ルール2は、すべてのパワープレーンやトレースには、過渡的な電磁波を束ねるために、ソリッドリターンプレーンが隣接していなければならないということです。ルール3は、すべての重要な信号には、ソースに戻るための明確なリターンパスがあるようにすることです。例えば、基板の上から下に向かって信号を流す場合です。重要な混在信号やワイヤレス設計では、限られた状況を除き、パワープレーンをリターンパスとして使用することはできません。これらのルールにより、スタックアップ設計が決まります。詳しくは、参考資料のリンク先の記事をお読みください。
ケネス・ワイアット:
回路機能の分割が重要になる主な理由であるため、まず、還流伝導電流の経路を確認しましょう。このコンセプトを緑の還流伝導電流でシミュレーションしてみました。左側の1キロヘルツの低周波数の例では、還流電流が広がっており、基本的には負荷から直接電源に戻る、いわゆる最小抵抗の経路になっていることがわかります。右の高周波(1メガヘルツ)の例では、還流電流が回路トレースの直下、つまりインピーダンスの最も少ない経路にあることがわかります。現在、ほとんどのオンボードDC-DCコンバーターは1メガヘルツ以上で動作しているため、還流電流は信号トレースのすぐ下を通る傾向にあります。還流電流のほとんどが100キロヘルツ以上の信号トレースと電源トレースの下で閉じ込められているので、分割の概念を使って、回路のさまざまな部分を分離することができます。この分割の概念は、アナログRFとデジタル回路の間で回路基板に注目する際に非常に重要になります。これについては、後で説明するスライドでご説明します。
ケネス・ワイアット:
PCBの中で信号がどのように動いているかについては、回路の視点とフィールドの視点という2つの視点があります。現実には、これら両者は関連し合っており、どちらか一方が欠けてもダメな存在です。今の回路理論は、信号や電源が元に戻ることだけにフォーカスしています。私は学部生の時にこれを叩き込まれました。低EMIのPCBの設計を理解するためには、電磁波という信号エネルギーがどのようにPCB内を伝播するかを考える必要があります。フィールドの観点から考えると、信号や電力の過渡場が光速に近い速度で誘電体空間を移動し、同時に伝導電流と変位電流が銅トレースとリターンプレーンの内面に沿って毎秒約1ミリの速度でソースに逆流することを理解する必要があります。重要な点は、信号エネルギーは銅ではなくフィールドにあるということです。
ケネス・ワイアット:
では、単純なマイクロストリップでは、デジタル信号はどのように伝搬するのでしょうか?断面図で描かれているのは、ソリッドリターンプレーン上のマイクロストリップです。左側にはゲートドライバー、右側には伝送線路の特性インピーダンスの抵抗負荷があります。100キロヘルツ以上では、デジタル信号は実際には、銅トレースとリターンプレーンの間の誘電体空間内を移動する電磁波であり、この例では、ゲートがハイからローの状態になると、左から右に向かって波面が伝播しています。ここで重要なのは、信号の伝搬は、従来から言われているように、銅の中の電子の流れによるものではないということです。電磁波によって誘導された伝導電流と変位電流は、それぞれ銅トレースとプレーンの内面に沿って、また絶縁体を介して変位電流として流れますが、その速度は毎秒1ミリ程度と非常に遅いものです。この伝導電流は、電流計で測定できます。
ケネス・ワイアット:
FR4絶縁体の場合、波は光の約半分の速度、ナノ秒あたり約6インチ(15cm)で伝搬します。私がレビューするほとんどの4層基板は、極めて一般的なものですが、ここに示されているように、非常にEMIリスクの高い構造を使用しています。まず注目すべきは、パワープレーンとリターンプレーンの距離がかなり離れており、良好な高周波数デカップリングが可能となっているため、電力の過渡現象が放射されることが期待されるという点です。最良の高周波デカップリングのためには、パワー層とリターン層は2〜3ミル以上離れている必要があります。2つ目に注目すべきは、パワープレーンを基準とした信号層があり、還流伝導電流はパワーではなく、リターンプレーンを通常基準にするソースに戻りたがっていることです。重要でない回路では、パワープレーンとリターンプレーンが非常に密接に結合しており、適切なデカップリングコンデンサーを使用している場合に限り、信号をパワープレーンの基準にすることが可能です。しかし、従来の4層構造の場合、このようなことはほとんどありません。
ケネス・ワイアット:
一般的な4層構造に対する解決策はおそらくたくさんあると思いますが、ここでは最小のEMIを実現するのに役立ついくつかの方法をご紹介します。それぞれ、各層に信号とルーティングされた電力を流しており、グラウンド基準プレーンが内層にあるか外層にあるかだけが違いとなっています。信号と電力を外層で流すことで、トラブルシューティングが容易になるというメリットがあります。一方、基準プレーンを外層に配置するメリットは、端部に縫い付けてファラデーケージ効果により、基板の自己遮蔽性を高められることです。
ケネス・ワイアット:
両方のデメリットは、重要なICの電源とリターンの各ピンに適切なデカップリングコンデンサーが必要になることです。本当に小さくて密度の高い設計では、最初から8層または10層の基板を重ねるのがベストです。左側に表示した最も一般的な左の6層構造にも同様の問題があります。まず注目すべきは、パワープレーンとリターンプレーンの距離がかなり離れており、良好な高周波数デカップリングが可能となっているため、電力の過渡現象が放射されることが期待されるという点です。それだけでなく、さらに重要なことは、パワーレールの過渡場が現象が2~4信号層と結合することです。
ケネス・ワイアット:
最良の高周波デカップリングには、パワープレーンとリターンプレーンは2〜3ミル以上離れている必要があります。近ければ近いほど良くなります。繰り返しになりますが、2つ目のポイントは、先程申し上げたとおり、パワープレーンを基準にする信号層があることです。右側の構造は、トランスミッションラインの基本的なルールに従っており、また、中央の電源層とリターン層の間隔をより狭くしてより良い高周波デカップリングを実現しています。このデメリットとしては、1層を失うことなどがありますが、いずれにしても、今日の高密度ワイヤレス製品では、最高の回路性能と最小EMIを実現するために、8層または10層が必要になるでしょう。
ケネス・ワイアット:
100キロヘルツ以上の周波数では、信号や電源のトレースの直下をリターン電流が流れる傾向があるため、この自己分離特性を利用して、主要な回路機能を分割してノイズの多い回路と静かな回路を分離し、なおかつ基板にはソリッドリターンプレーンを使用することができます。例えば、電子処理部とRF部を分離することで、関連するノイズのリターン電流が敏感な受信機と結合するのを防ぐことができます。青色の線で配電を示していますが、実際には、3.3Vの主要電源にはソリッドパワープレーンを使用するのが一般的で、システムの電力要件に応じて、オプションでボード全体に配電することができます。すべての電子処理回路の下にソリッドパワープレーンを設置し、リターンプレーンへのデカップリングコンデンサーを十分に使用することが必要です。
ケネス・ワイアット:
単純化された図のように、回路機能を分離することは必ずしも現実的ではありませんが、無線モジュールや携帯電話モジュールから既知のノイズ源を分離することは非常に重要です。ワイヤレス回路をすべてまとめて、ノイズの多い電子処理や電力変換器から離すことを目指します。また、電力コンバーターを別ブロックとして示していますが、電力コンバーターは入力コネクターの近くや、電源の近くに配されることもあります。DC-DCコンバーターは、無線モジュールから遠ざけます。
ケネス・ワイアット:
2つ目のアドバイスは、低EMIのコンバーターを使うことです。Texas Instruments社も、Analog Devices社やLinear Technologies社も、低EMIのコンバーターを開発し続けていますし、他のメーカーも同様に取り組んでいるはずです。例えば、Texas Instruments社は入出力コンデンサーをパッケージの近くに配置することができる新しいQFNパッケージを開発しました。また、その中にはスイッチされた駆動電圧のスルーレートを制御する手段も含まれています。Analog Devices社が開発した「サイレント・スイッチャー」は、入出力コンデンサーを、特にICパッケージの近くに配置することにも対応しています。最近発売されたサイレント・スイッチャー 2では、低EMIコンバーターが、入出力コンデンサーとその関連ループをICパッケージ内に組み込まれています。さらに、同社のマイクロモジュールデザインには、スイッチングコンデンサーも組み込まれています。高価ではありますが、これらはいずれもワイヤレス機器のEMIに対して特に静かに動作します。最後に、多くのコンバーターでは、平均EMIをさらに低減することができる、スペクトラム拡散クロックを使用することができるようになっています。
ケネス・ワイアット:
3つ目のアドバイスは、コンバーターの回路を同じレイヤーに置くことです。ノイズ結合の原因として、高速のスイッチング信号が基板の上から下に流れることが挙げられます。あるお客様の基板では、降圧コンバーターの回路が最上層に、出力スイッチングコイルが最下層に配置されていました。その結果、3メガヘルツのスイッチング電流が上から下へ、そしてまた上から下へと流れ、オンボードGPSの認識を妨げるのに十分な干渉が発生していました。
ケネス・ワイアット:
4つ目のアドバイスは、コンバーターの回路をICに近づけることです。DC-DCコンバーターには、図のように入力電流ループと出力電流ループが必ず存在することを説明しましたが、これらのループ領域は最小化する必要があります。IC製造業者は、EMIが問題であることを認識し、設計者に警告し始めています。コンバーター製造業者はよく、データシートの最後に推奨レイアウトを掲載しています。推奨されるレイアウトは、2~3年前のものでも不正確なことが多く、それ以上前のものだと大抵不正確です。これらのループを最小限に抑えるためには、入出力コンデンサおよび出力インダクタは、できるだけICパッケージの近くに配置する必要があります。もう1つのポイントは、基板レイアウト上でコンバーターの入力回路と出力回路を混在させないことです。一次側と二次側の回路をできるだけ分離することをお勧めしています。最後に、入力コンデンサーと出力コンデンサーが同じ還流電流経路を共有しないようにします。
ケネス・ワイアット:
私の仲間であるwww.learnemc.comのトッド・ハビング博士は、DC-DCコンバーターのレイアウトに関する優れたプレゼンテーションを行っています。ハビング博士のサイトへのリンクは、参考資料のセクションをご覧ください。5つ目のアドバイスは、グラウンドリターンプレーンがソリッドであることです。高速スイッチング信号やコンバータートレースがグラウンドリターンプレーン内のギャップやスロットを通過すると、基板全体でEMIが結合され、感度の高いレシーバに影響を与える可能性があります。私のウェブサイトでは、リターンプレーンにギャップがあるとEMIに悪影響を及ぼすことを説明した短い動画のデモを公開しています。右側のスクリーンショットでは、ギャップのあるリターンプレーンとギャップのないリターンプレーンの放出の違いを見ることができます。
ケネス・ワイアット:
リターンパスのギャップ周辺でリターン電流が強制されると、EMIが15~20dBほど増加します。リターンプレーンのボイドを、スイッチノードとスイッチコイルのどちらかの下に置くのが良いのか、両方の下にボイドを置くのが良いのか、それともソリッドリターンプレーンを維持するのが良いのか、という議論が続いていました。Picotest社のスティーブ・サンドラー氏は、それぞれの構成で降圧コンバータ回路基板を作成しました。私は、電源入力に電流プローブを当てたり、同相モードまたは異相モードのEMIだけを抽出する機能を持つLISNを使ったりして、さまざまな方法で測定してみました。いずれの測定でも、ほとんどの周波数において、少なくとも測定誤差の範囲内では、ソリッドプレーンが総合的に勝っていました。ほとんどの場合、その差は2〜3dBとわずかなものでしたが、これでもギリギリのところにいる場合は、基準に準拠するかしないかの分かれ目となります。
ケネス・ワイアット:
6つ目のアドバイスは、スイッチングまたは出力コイルをシールドして、磁界を閉じ込めることです。左の断面図では、左半分の巻線がさらにフェライトで覆われていて、磁界がギャップ部分だけに拘束されているのがわかります。右の断面では、電界線はシールドされていないので、自由に放射したり、他の回路と結合したりすることができます。パトリック・デロイ氏のプロットとシミュレーションでは、かなりの違いが見られます。基本的には、巻線が見える場合はシールドされていません。こちらもパトリック・デロイ氏による、シールドされたコイルとされていないコイルの磁界の違いを示すプロットです。ここには15~20dB程度の差があります。
ケネス・ワイアット:
7つ目のアドバイスは、低EMIの方向に出力コイルの向きを変えることです。以外と知られていないことですが、コイルの巻線には始点と終点があります。始端子は、ボディの上部に半月やドット、ラインなどで印が付けられていることがあります。例えば、Würth Elektronik社の端子では、ラインやドットが付けられている傾向があります。TDK社は半月をよく使用しています。巻線の始点は巻線に埋もれているため、巻線により多少遮蔽されます。DC-DCコンバーターICのSWとラベルされているスイッチドノードと向きが合うよう、巻線の始点の向きを調整します。巻き終わりは出力フィルターにつながっているので、巻き始めに比べてより静かであったり、フィルターがかかっていたりします。PCBの専門家であるリック・ハートリー氏によると、これによりEMIを2〜3dB低減できる可能性があります。
ケネス・ワイアット:
8つ目のアドバイスは、ローカルシールドに合わせて計画することです。遮蔽性の高いコイルを使用したり、適切な基板設計やレイアウトを行ったりしても、回路ループや出力コイルの周辺には強いH-Field、特にE-Field電界が発生してしまいます。グラウンドリターンプレーンに接続されたフェンシングソルダーストリップを追加することで、最初からこれらのローカルシールドに対応するようにPCBを設計することができます。また、プロセッサーやメモリのICの周りにもこれらを追加する必要があるかもしれませんが、もし必要なければ、素晴らしいことです。Würth Elektronik社やLayad社など、多くのメーカーがこれらの標準およびカスタムのローカルシールドを製造しています。私の経験では、最初からソルダーストリップが設計に組み込まれていない場合、半田の仮シールドを取り付けるのは非常に難しくなります。
ケネス・ワイアット:
こちらはパトリック・デロイ氏による別の測定結果で、PCBの1cm上にローカルシールドを使用することでE-FieldとH-Fieldで減少できることを示しています。左の写真では、E-Fieldでかなり劇的に減少しているのがわかります。このE-Fieldは、シールドされていない場合、ワイヤレスアンテナに直接放射される可能性があります。これは、Samsungのエンジニアがローカルシールドの使用について調査した結果です。右側のシールドされた電話機にはほとんどフィールドがないことに注目してください。現在の携帯電話の多くは、回路のほとんどに多重のローカルシールドを使用しています。
ケネス・ワイアット:
9つ目のアドバイスは、RF吸収体を使うことです。その1つが、フレキシブルなフェライトを搭載したRF吸収体です。私には長年にわたって集めてきたかなりのコレクションがありますが、初期の実験では携帯電話の周波数ではほとんど役に立たなかったようです。このアドバイスについて数枚のスライドで説明します。なぜなら、受信機モジュールへの内部結合を減らすための真のチャンスがあると信じており、他の人にもこの素材で実験してみることを勧めたいからです。Würth Elektronik社は、アプリケーションノートANP059を発表し、用途に応じて、RF吸収体の特性を3つの方法で評価できることを説明しています。電磁界を吸収するために最も有効なのは、スライドで紹介したマイクロストリップ方式でした。この技術は、マイクロストリップを使って、フェライト材を上に敷いたときの減衰量を測定します。高周波高調波成分のあるデバイスやトレースに吸収体を装着することで、放射電界を抑制することができます。
ケネス・ワイアット:
ほとんどのメーカーは、私が必要とする種類の吸収データを提供していないようでしたので、600から1500メガヘルツの範囲で有効な材料を特定するために、スケーラーネットワークアナライザーを設置して、手持ちのすべてのサンプルの特性評価を始めました。ほとんどのサンプルはマイクロ波の周波数でしか効果がないことがわかりましたが、一般的な無線や携帯電話の周波数で効果があるものもいくつかありました。各サンプルを50Ωのマイクロストリップの上に置き、結果を記録するだけなので、テストはとても早く終わりました。この研究の結果も、参考資料セクションでご覧いただけます。重要なワイヤレスやGPSの帯域では、Parker-Chomerics社のSS4850 0100 0150 300とArch Techs社のWAVE-X WXA20の2つの吸収材が最適でした。携帯電話が使用するLTE帯域では少なくとも10dB、GPSが使用する帯域では最大20dBの吸収が各素材で確認できます。
ケネス・ワイアット:
今回のケーススタディでは、いくつかの帯域にあるセルラーデセンスを減らすためにクライアントをサポートしました。自動発生するEMIの原因となるエネルギー源は数多くあります。今回の実験では、DDS RAM、RFで発熱するフレックスケーブル、複数のDC-DCコンバーターを搭載したパワーマネジメントICの上に、自己粘着性のあるArc Tech WAVE-X WXA20パッチを貼り付けました。小さな赤い「X」がついている部分です。
ケネス・ワイアット:
このIOT機器の場合、セルラーアンテナは上下に、GPSとWifiのアンテナは側面に配置されていました。AT&T社の帯域であるLTE帯域5のちょうど真ん中あたりで、PCBの側面から強い映像信号が漏れていましたが、3枚の小さな吸収体パッチを貼った後、その強い信号は少なくとも15dBはノイズフロアにまで落ち、携帯電話の受信感度が大幅に改善されました。DC-DCコンバーターのような高周波エネルギー源に対処する際に、フェライトを搭載した吸収体を使うことには多くのチャンスが秘められています。問題は、この材料のほとんどがマイクロ波帯用に設計されており、ほとんどのIoT機器が使用する帯域では効果がないということです。
ケネス・ワイアット:
10個目のアドバイスは、アンテナや同軸ケーブルは、DC-DCコンバーターやその他のケーブルから離して設置することです。アンテナやそれに付随する同軸ケーブルを使用する場合は、DC-DCコンバーター、プロセッサー、IOケーブル、または電源ケーブルからできる限り離して設置してください。前のスライドで見たように、電圧降下の大きいバックコンバーターの入力回路ループは、dV/dtが比較的高くなり、それに伴う電界が直接受信アンテナと結合してしまいます。また、IOケーブルや電源ケーブルは、基板上で発生した同相モード電流を直接アンテナと結合する可能性があります。
ケネス・ワイアット:
さて、おまけとして11個目のアドバイスですが、ICメーカーのデータシートを信用してはいけません。データシートが正確な場合もありますが、EMC設計やレイアウトに関するアドバイスが間違っていることもよくあります。ここではTexas Instruments社の例をいくつか紹介します。また、誤った設計情報を提供しているのはTexas Instruments社だけではないと考えてください。多くの企業が誤ったものを提供しています。左は、TI TPS54308のソリッドリターンプレーンが不明確です。スイッチノードは基板上をくまなく走り、入力コンデンサーと出力コンデンサーは同じグラウンドリターンパスを共有しています。スイッチノードは最小限の面積で、ICの近くに配置される必要があります。
ケネス・ワイアット:
右側のTI LMR 33630のレイアウト案でも、入力コンデンサーと出力コンデンサーが同じグラウンドリターンパスを共有しています。これは、スイッチング電圧を2次パワーレールと直接結合する優れた方法です。トッド・ハビング博士は、2020年に開催されたシンポジウム「IEEE Symposium on EMC and SIPI」において、メーカーのデータシートやアプリケーションノートに関する優れた論文を発表しました。また、同博士は、learnemc.comの講座でもこのトピックを取り上げています。ここでは、EMIが自動発生し、TISの受信感度テストに影響を与えている場合に試すべきことをまとめてみました。何十件ものクライアントのプロジェクトに携わった経験から、これらの実験の中には問題を特定するのに役立つものもあれば、そうでないものもあります。ここではリストに記載されているすべての項目について説明するのではなく、どのDC-DCコンバーターが受信機と結合するかを明確にするためのいくつかの方法をご紹介したいと思います。
ケネス・ワイアット:
ほとんどのIoT機器は、3~5本のパワーレールを必要とする組み込みプロセッサーを使用しているため、どのコンバーターが主にEMIを発生させているかを判断するには、バッテリーに交換したり、3端子のリニア電圧レギュレータを追加したりすることが非常に有効な手段となります。スイッチングコイルを基板から取り外し、パワーレールに接続するだけなので、思ったよりも簡単です。コイルを取り外すと、スイッチング動作が停止します。私たちはバッテリーパックにショットキーダイオードを直列に接続して適切なレベルに落としたり、3端子のリニア電圧レギュレータを半田付けしたりしました。EMIのソースを特定したら、PCBのその部分に焦点を当て、結合しているパッドを特定することができます。
ケネス・ワイアット:
以上のことから、最高のレシーバーのTIS性能を実現するためには、適切な構造とパーティショニングにより、可能な限り最高の基板設計を行う必要があります。また、DC-DCコンバーターの回路を最上層に密に配置し、その下にソリッドリターンプレーンを配置する必要があります。DC-DCコンバーター、プロセッサー、メモリなどの高エネルギー源に対する局所的なシールドがおそらく必要になるでしょう。放射トレース、プロセッサー、RAM、DC-DCコンバーターなど、既知のエネルギー源にRF吸収体を加えてみてください。また、無線や携帯電話のアンテナを適切に配置することも重要です。
ケネス・ワイアット:
ここでは、私自身の役に立ったいくつかの資料と、より深く掘り下げた私の記事をご紹介します。自動発生するEMIは、ワイヤレスや携帯電話向けIoT製品を開発しているメーカーにとって長年の課題でした。これらのアドバイスが、ワイヤレスや携帯電話の受信機での低EMIノイズを実現するのに役立つことを願っています。ワイヤレス機器におけるEMI問題のトラブルシューティングや、EMCに関する一般的なトラブルシューティングについては、design-4-emc.comや、EDM、またはinterferencetechnology.comの私のブログか、Amazonで紹介される私の書籍情報ページをご覧ください。