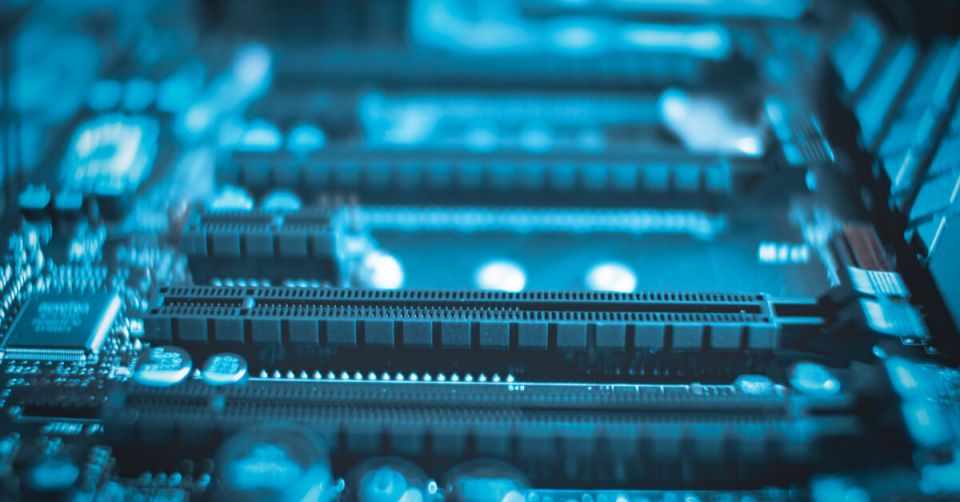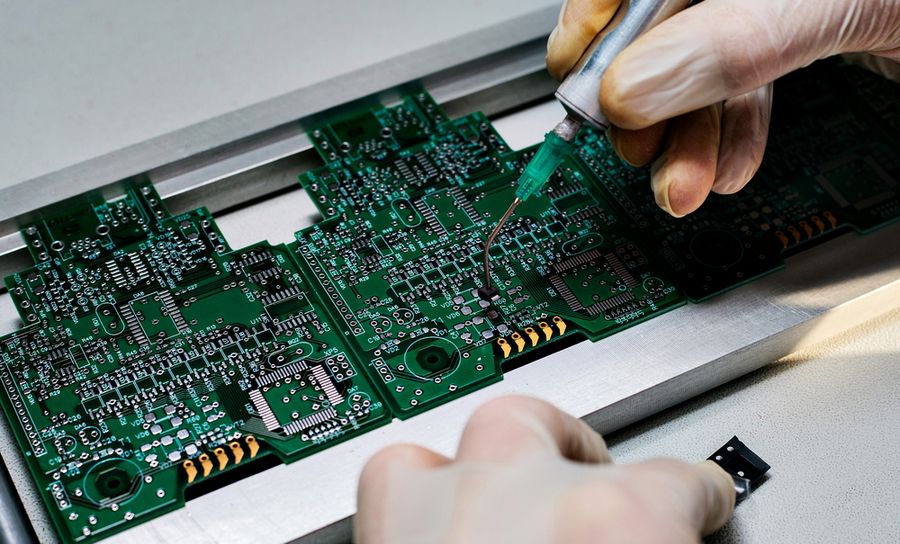PCB Design and Layout
Create high-quality PCB designs with robust layout tools that ensure signal integrity, manufacturability, and compliance with industry standards.
Filter
見つかりました
Sort by