測定されたSパラメータの専門家による分析

はじめに
Sパラメータ解析に関するチュートリアルは数多くあります。通常、ポートマップの特定方法、挿入損失と戻り損失の見た目、さまざまなSパラメータが時間領域でどのように見えるか、といったトピックが含まれます。初心者にとってはこれが非常に価値があります。ここでは、これらのトピックを簡単に説明し、Sパラメータをデータマイニングする際に使用する追加の分析技術についていくつか紹介します。
Sパラメータの簡単な概要
Sパラメータは基本的に伝達関数です。周波数領域での刺激、例えばパルスをSパラメータに乗じると、そのパルスがSパラメータで表されるチャネルを通過した後の応答が得られます。チャネルは、ケーブルのような受動チャネルやCTLEのような能動チャネルなどがあります。
基本的な考え方は、このブラックボックスを通して信号を送った後に何が起こるかを理解するためにSパラメータが使用されるということです。2ポートSパラメータでは、S21とS12は挿入損失または伝送パラメータであり、おおよそ同じであるべきです。S11とS22は返り損失または反射パラメータです。デバイスが非対称である場合、これらはユニークになることがあります。これらは通常、電圧dBでプロットされます。
ここで、Aは入力Sパラメータです:S21、S11、など。

この例では、S21とS12は実質的に同一です。S11とS22には、S11には存在しない18GHz周辺のS22の大きな共振のような、いくつかの顕著な違いがあります。
ここで、私があなたに最初に追加の知識を提供したいと思います。Sパラメータの大きさをdBで見るだけでなく、位相も見てください。位相は次のように計算します:
また、位相をアンラップする必要があります。位相をアンラップするとは、位相が2 x PIだけシフトするたびに2 x PIを加算または減算して、位相が直線のように見えるようにすることを意味します。下の左のプロットはラップされており、右はアンラップされています。
 |
 |
|---|
位相はいくつかの質問に答えることができます:
- このデータを時間領域に持ち込むには十分なデータがありますか?
- このデータは、測定された全周波数帯域にわたって有効ですか?
- この構造の遅延は何ですか?
これらを一つずつ見ていきましょう。
このデータを時間領域に持ち込むには十分なデータがありますか?
これらの質問に答えるために、伝送パラメーター、S21に注目します。位相は、DCから最高利用可能周波数まで、負の傾斜で単調に動くべきです。つまり、-πからπへのシフトの間に、アンラップする前に1点以上が存在することを意味します。シフト間に1点以下しかない場合、周波数から時間への変換を行うときに、エイリアシングと呼ばれる現象が発生します。これらのSパラメーターを時間領域に変換すると、データは通常より短く見えたり、さらには非因果的(t=0より前の情報)に見えたりします。このようなシナリオでは、時間領域の情報は基本的に使用不可能です。これらの場合、アンラップされた位相は、DCから最高周波数まで正の傾斜を持ち、その例を以下の図xに示しています。この問題を解決するには、より小さい周波数ステップでSパラメーターを測定します。一般に、10 MHzステップのSパラメーターでは、この問題は発生しません。

このデータは、測定された全周波数帯域で有効ですか?
この質問に答えるために、いくつかの測定データを見てみましょう。
 |
 |
|---|
左側のデータはデシベルで、右側はアンラップされた位相です。挿入損失では、15 GHz付近でデータが不鮮明になるのが見て取れますが、戻り損失は問題ありません。位相を見ると、負の傾きを持って始まり、これは良いことです。そして、16 GHz付近で傾きがゼロになるのが見て取れます。これは、SパラメータがVNAのノイズフロアに達し、VNAが位相を取得できなくなるためです。傾きがこのように0になると、Sパラメータは無効です。これを修正することは常に可能ではありません。VNAのノイズフロアは、IF帯域幅設定によって約80から110 dBです(IF帯域幅が低いほど、ノイズフロアも低くなります)。時間領域のVNAは、ノイズフロアが-40dBに近いです。
構造の遅延はどのくらいですか?
シグナルインテグリティエンジニアは通常、ステップ応答で時間領域内の遅延を測定します。彼らはTDRからの入力ステップの50%クロッシングを測定します。その後、試験中のデバイスを通過した出力の50%クロッシングを測定します。この方法には、ステップ応答の導関数を取り、50%クロッシングの代わりに各ピークの遅延を測定するといった人気の修正があります。また、ステップの相対振幅ではなく、固定電圧でのクロッシングを測定する方法もあります。最後に、5%ポイントなど、異なるクロッシングで測定することもできます。
これらはすべて良い点ですが、もっと良くできることがいくつかあります。まず、遅延測定に異なるテスト機器を使用するという考え方です。1つだけで済む方が良いでしょうし、VNAがノイズフロアが低いことを考えると、VNAが明らかに選択すべき測定装置です。次に、ラボ間の一貫性です。VNAは、Short-Open-LoadおよびUnknown-Thru校正を用いて、NISTトレーサブルな参照面を容易に実現できます。TDRの校正はNISTトレーサブルではなく、これがラボ間の相関を非常に困難にしています。最後に、データ転送があります。時域デジタルデータには標準フォーマットがなく、通常はExcelスプレッドシートで共有されます。VNAデータには、広く使われているタッチストーンファイルを含む多くの標準フォーマットがあります。実際にすべてのEDAツールはタッチストーンファイルを受け入れ、このフォーマットが利用可能であることはコミュニケーションを大幅に容易にします。ですので、VNAを使用し、そこから遅延をどのように得るかを見つけましょう。
最初の方法は、TDRが行うのと同じ、周波数から時間への変換を行うことです。これにはいくつかの利点があります。まず、伝達関数を積分してステップ応答を得ることができます。この方法では、入力ステップを最初に測定する必要がなく、2つではなく1つの遅延のみを測定すればよいのです。このアプローチに対する反論は、周波数から時間への変換から得られる点が少なく、不確実性が大きすぎるということです。これは妥当な点ですが、チャネルを通るステップ応答の傾きは非常に一貫しているため、最も近いピコ秒まで補間するのは非常に簡単です。ステップの傾きはあまり変わらず、正確な補間データを得るのは非常に簡単です。
| ステップ応答 | ズームイン |
|---|---|
 |
 |
赤は生データで、青はスプライン法で補間されたものです。データカーソルは、生データからの50%クロッシング周辺の離散点です。
「そうは言っても、周波数から時間への変換や補間のやり方がわからないよ」と思うかもしれませんね。しかし、VNAを使えばそれがさらに良い点です。なぜなら、その必要がないからです。もう一度位相を見てみると、遅延を得るための簡単な式を適用できます。
この方程式の素晴らしい点は、ギガヘルツで周波数を割るだけで遅延をナノ秒で得られることです。

まず、ステップ応答プロットでx軸と同じスケールでy軸をプロットしたことに注目してください。ステップ応答では、遅延は周波数ドメイン法ほど一貫性がありません。10 GHzから50 GHzまで、遅延は基本的に同じです。これにより、この方法はラボ間で非常に一貫性があります。次に注目すべき点は、示されているように、25 GHzでの遅延がステップ応答のそれと少し異なることです。これは、50%の遅延がこのプロットの低周波数で見つかり、そこでは位相が各点で急速に変化するためです。これはまた、ステップ応答法がラボ間の相関にあまり信頼できない理由のもう一つです。また、交差点の代わりに使用する周波数点を選べること、それがはるかに曖昧さが少なく、補間の必要がないことも気に入っています。
スキューを迅速かつ簡単に計算する
デバッグチャネルの際、スキューは最初にチェックすべき事項の一つです。スキューとは、差動伝送線の正と負の側面の遅延差のことです。伝送線が緩く結合されている場合、このトリックを使って非常に迅速にスキューを計算することができます。まず、単一終端Sパラメータをモード変換に変換します。別の言い方をすると、SからSCDへの変換です。次に、SCD21データをdBでプロットし、最初の最小値を見つけます。

その周波数の逆数がスキューです!これが以前に議論された遅延方法とどのように一致するか見てみましょう。
ライン1の遅延:1.38482356955646ns
ライン2の遅延:1.42117027815264ns
遅延の差(スキュー):0.0363467085961828ns
SCD21から計算されたスキュー:1/27.52 = 0.0363372093023256ns
誤差:9.49929385720555e-06ns(ほぼゼロ)
このトリックは、スキューが比較的大きい場合(>50 ps)にのみ通常機能します。
共通モードが何を伝えているか、ということですか?
コモンモードは、しばしば見過ごされるパラメータです。電磁干渉(EMI)の議論の際に、伝送線内の漏れを見つけるために取り上げられます。しかし、コモンモードは、何を見ているのか、構造がどのように機能しているのか、そしてどこで問題が発生する可能性があるかを理解するのに役立ちます。
まず、周波数領域でのコモンモードを見てみましょう。ここでは、コモンモード挿入損失と差動挿入損失を比較したいところです。これは、信号の戻り経路が信号のみと比較してどのように振る舞っているかを比較します。この方法でストリップライン差動ペアを見ると、コモンモードと差動モードが似たような振る舞いをしているのがわかります。このタイプの振る舞いはツイン軸ケーブルでも期待できます。

チャネルにインターコネクトが配置されると、状況は異なって見え始めます。コモンモードは挿入損失から逸脱し始めます。この場合、20 GHz近くで、この逸脱が存在する周波数で増加した放射やクロストークを見ることが期待されます。

もう一つの見るべき場所は、インピーダンスです。共通モードインピーダンスは25オームに基づいています。インピーダンスが25オーム未満の場合、信号は完全に非結合であり、差動伝送線のインピーダンスは100オーム未満です。これは、多くのインテグレーターがスキューの緩和に役立つ「緩く結合された」差動ペアを使用することを好むため、システムではかなり典型的なシナリオです。インピーダンスが高い場合、ペア内の結合が増加しています。これはまた、グラウンドが飢餓状態になり始めていることを示すこともあります。結合されたストリップラインでは25オームから28オームのインピーダンスが期待され(下の図を参照)、ツイン軸ケーブルでは32オームまで高くなることがあります。インターコネクトの共通モードインピーダンスは比較的高いことがあります。例えば、QSFPコネクタは共通モードインピーダンスが50オーム近くになることが知られています。これはほとんどのシステムにとって問題ではなく、分析を行う際にこの挙動を知っていると、問題を探している際にインターコネクトのどこを見ているかを理解するのに役立ちます。

次のPCB設計でAltiumがどのようにあなたを支援できるかについてもっと知りたいですか?Altiumの専門家に相談してください。

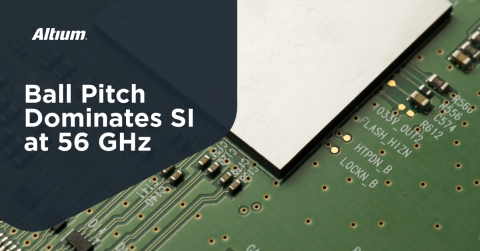



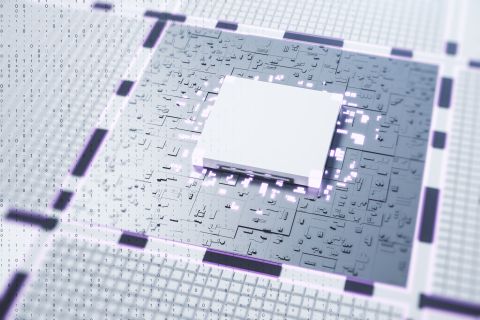

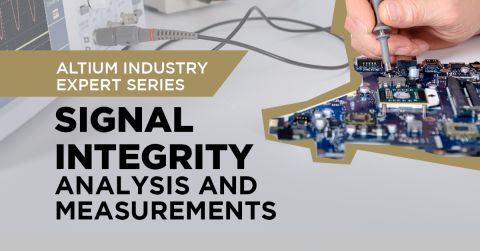

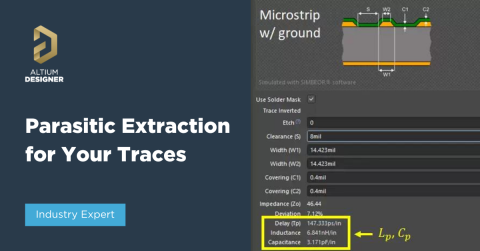

 Back
Back